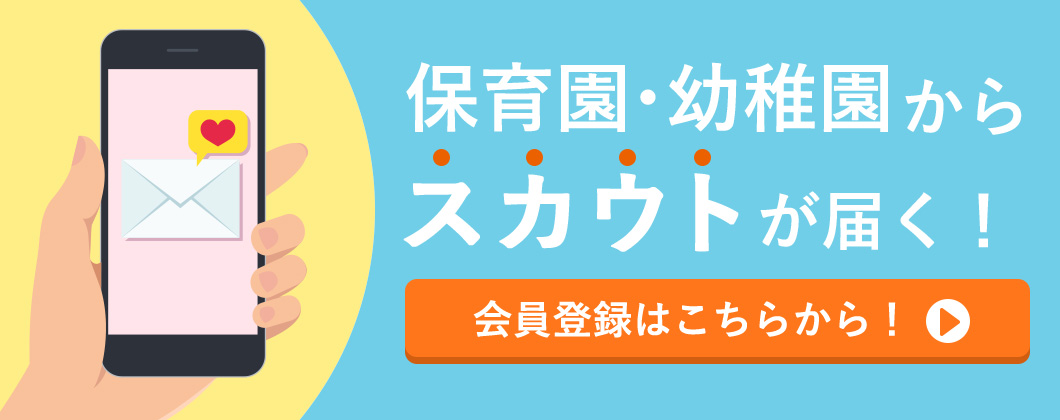保育コラム
見守るべき子どもの喧嘩の見分け方は
保育士さんなら遭遇しても決して珍しくないのが「子どもの喧嘩」です。
保育園に預けられている子どもたちは毎日、集団生活をしていて小さなコミュニテイの中で生活しています。
とっても気の合う友だちもいればそうでない子どももいるでしょう。
しかしこの「子どもの喧嘩」、一体保育士としてどう関わればいいのか悩んでしまうことも多いですよね。そもそも、止めたほうがいいのか、自由に見守っておいて当人たちで解決できる力をつけさせたほうがいいのか・・・というところも迷ってしまいます。
今日は、「見守るべき喧嘩の見分け方」についてご紹介いたします。
子どもの喧嘩の仲裁に入る前にすること
まず、子どもの喧嘩の対応として始める前に毎日の保育を振り返ってみましょう。
あなたはクラスの子どもたちときちんと信頼関係を築けていますか?
あなたがいい加減に向き合っている子どもにはあなたの言葉は届きにくくなっています。
同じ仲裁でも、信頼関係が築けているのといないのとでは子どもの反応が違うでしょう。
そこで、あなたは毎日の保育において子どもの話し、そして子どもの気持ちに真摯に寄り添うことが必要です。
普段からそういった態度をとっていることで、子どもは喧嘩をして高ぶった気持ちを包み隠さず保育士にいって来てくれます。
「この先生は分かってくれない」と子どもに思わせないことが、喧嘩の対応がすんなりできるようになる近道です。
見守ってもいい喧嘩は
子どもの喧嘩は当たり前
子どもは喧嘩をするものです。
毎日全く喧嘩をしないクラス、というのがあったら見ていたいと思うほど喧嘩をします。
もし、本当にあなたのクラスの子どもたちが喧嘩をしたことがない、というのなら少し気をつけた方がいいですね。
年齢にもよりますが、喧嘩というのは他人への興味が出てきた証拠です。自我がめばえ、他人への興味がわいているからこそ喧嘩が起こるのです。
そのため、喧嘩がない=自我の発達が十分でないか、他人に関心がない、ということです。
程度によっては、発達障害を疑うこともあります。
そんな喧嘩をしてしまいやすい子どもたちですが、その原因は取るに足らないものが多いのです。おもちゃを貸してくれなかった、何気ない一言をいわれた、そんなちょっとしたことで火がついたように怒り出し、つかみ合いの喧嘩になります。
しかし本人同士にしてみれば、その時はとても大切な原因で、「許せない!」と感じてしまうものです。
そこで、相手に危害を加えたりするような喧嘩でなければ保育士はあえて仲裁に入らない方がいいのです。
見守るべき喧嘩の例
例えばおもちゃの取り合いです。
喧嘩の原因としては最も多いかもしれません。
この時、保育士が早めに仲裁に入ると、子どもたちは心が憤ったままです。相手の気持ちを考えたり、相手の話を聞く機会がなくなってしまい、同じ状態になったときにまた喧嘩が勃発してしまいます。
しかし、保育士が根気強く見守ってみるとどうなるでしょうか?
子どもたちは自分たちだけで考え、どうすればいいのか解決策を生み出してくることもあるんです。一緒におもちゃを使うために、順番をきめたり、使う長さを決めたりというルールづくりをしたり、そのルールを守れるように声掛けをしたり、ルールを守るべきという道徳性も身についていきます。
もちろん、これらのことが出来るようになるには年齢にもよります。
1~2歳児でもおもちゃの取り合いの喧嘩はあります。しかし、1~2歳はまだルールづくりや話し合いなどをすることができません。
この時、見守っているだけではきっと引っかいたりのトラブルに発展するでしょう。
まとめ
保育士は、子どもたちを安全に預かることが第一です。しかし、同じくらい「正しい発達を促す」ということも大切です。
喧嘩の仲裁では、年齢や状況を見極めながら対応することが非常に大切になります。
自分たちで解決できそうな原因か?解決のために必要な発達が完了している年齢か?ということを常に観察するようにしましょう。(寄稿元:保育士の子どもとの接し方テクニック – http://www.tubudol.com/)
保育の仕事の人気ランキング
おすすめ記事
人気ランキング
人気記事ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
公認ブロガー寄稿
-
保育士を辞めた人が遭遇する厳しい現実と対策
2017.01.05
特集
-
「これだけかよ…」 私が保育士辞めたい理由
2016.09.18
特集