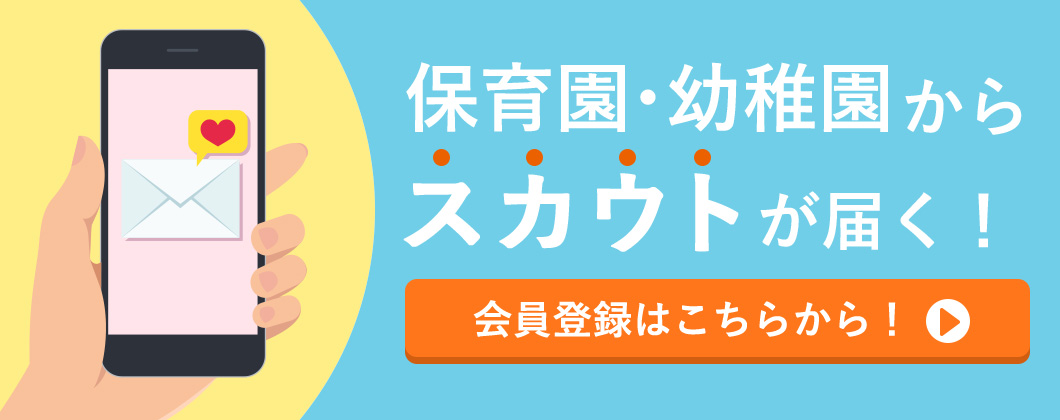保育士の転職
「小さな失敗」から、予測できないことに立ち向かう
Profile ゆきせんせい
現役保育士。元は一般事務員だったが、3人の息子が大きくなったのを機に一念発起、資格を取り、保育士として働き始める。毎日、保育園の子どもたちからは元気を一杯もらって、保護者のパパやママたちには子育ての先輩としてエールを送っている。
チャイコフスキーのバレエ組曲「白鳥の湖」でもおなじみの黒鳥。
最近ではアフラックのCMにも出ていますよね。

実はこの黒鳥、かつては「存在しないもの」だと信じられていました。
英語のことわざで「黒い白鳥(ブラックスワン)をさがすようなもの」というものがありますが、これはそれまで黒い白鳥はいないと信じられていたから生まれたことわざです。
ですから1697年にオーストラリアで黒鳥が発見された時は、それはもう大変な騒ぎだったそうです。
このことから、「今までの知識や経験から予測できないようなことが起こり、それが大きな影響を与えること」が『ブラックスワン』と名付けられました。
そして、最近話題になっているという、ナシーム・ニコラス・タレブの「反脆弱性――不確実な世界を生き延びる唯一の考え方」という本の中では、いかにして予想できないことに立ち向かうかということが書かれています。
保育に全く関係なさそうな話ですが、実はこういうことはどこでも起こりうるのです。一度起こって対処した事柄には慣れているので次はもっとうまく対応できると思うのですが、同じ問題はほとんど起こりません。
日々新しい問題が起こり、日々新しい問題に対応することが求められますよね。
このことに少し疲れた気持ちでいた時に、前出の本を知りました。
私の周りだけに事件が起きているのではない、保育園だけが問題が起こるわけではない、どこでも信じられないような予測不可能なことが起きているんだ。ということが分かると、少しほっとしました。
人間相手の場合は経験則が知識に勝る
たとえば、小さな子は小さな穴に手を入れるのが大好きです。
子どもが、目の前にあるコンセントを指でつついている光景をよく目にします。
コンセントの穴は小さく、いくら小さな子供であっても指を入れることはできません。ですからそれを見ても「どうせ指は入らないから」と見逃してしまいそうです。
しかし、むかし私の主人はコンセントに針金を突っ込んで感電したことがあるそうです。ですから我が家では使っていないコンセントにはカバーをつけていました。
感電は軽い事故ではありませんが、失敗から学び重大な事故を防ぐことができています。
保育園でもこういった事故が起こらないとも限りません。
また、ある時は顔に大きな赤い斑点がでている子がいました。
その時は特に不調も訴えていないことから様子を見ようという話になったのですが、私の妹が子どもの頃、卵を食べるとよく赤い斑点が出ていたことを思い出し、保護者の方に病院の診察を受けることをお勧めしたところアレルギーだと判明しました。
これも過去の経験から重篤な症状が出るのを防いだ事例のひとつです。
このように人間相手の場所では、いままでトライアンドエラーで得た「よくわからないけど、どうやらこうやるとうまくいくみたい」ということが驚くほど多いのです。後になって理論的に正しいと証明されることもありますが、先人のトライアンドエラーは知識にも勝るのです。
「ヒヤリ・ハット」の法則
子育て経験がある私や、保育経験の長い人にはこのようなトライアンドエラーで得た経験則を積み重ねていますが、若い保育士さんはまだそういった経験が少ないですよね。
そんな若い保育士さんのために、保育園でも最近「ヒヤリ・ハット」を報告するようになっています。
これは、1つの重大事故の背後には29の軽微な事故があり、その背景には300もの異常があるという経験則から生まれています。
「幸い事故に至らなかったけれど、こういうことが危険につながりそうだった」ということを共有して、重大事故に至らないように未然に防ぐのが目的です。
このように、自分のうまくいかなかったことを報告するのは勇気がいります。ややもすれば「ちゃんとできてないじゃないか」と指摘される可能性もあります。また、ただでさえ多い書類がまた増えることで保育士の負担にもなります。
しかしタレブの「反脆弱性」の中には、21世紀に成功する方法として「小さな失敗から学ぶこと」が大切だと書いてあります。小さな失敗を恐れて失敗しないようにしたり、放置したりすることはとても危険です。
大企業ですらこの「小さな失敗から学ぶ」ことに失敗すると倒産してしまうのです。
チャレンジの全てが自分の糧になる

新しい年度が始まって半年弱、そろそろ新しい職場、新しいクラス、新しい人間関係にも慣れてきた時期。これから運動会やお遊戯会などの行事も増えます。できるだけ多くのことにチャレンジしていきましょう。
チャレンジして成功したことも失敗したことも一つ一つが次の自分の糧になります。
そして、それこそが将来の成功や失敗を防ぐ唯一の方法なのです。
少し経験を積んだ私たちも、そんな若い人のチャレンジを見守ることのできる余裕と懐の深さを持っているか、胸に手を当てて振り返ってみたいものですね。
保育の仕事の人気ランキング
おすすめ記事
人気ランキング
人気記事ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
公認ブロガー寄稿
-
保育士を辞めた人が遭遇する厳しい現実と対策
2017.01.05
特集
-
「これだけかよ…」 私が保育士辞めたい理由
2016.09.18
特集