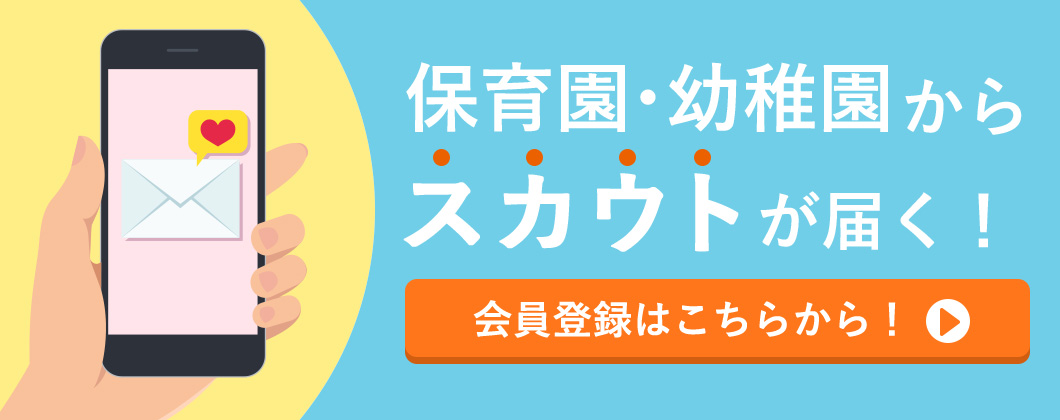保育コラム
保育園で気になる子どもの咳、どうやって対処したらいい?
子どもの咳のなかには大きな病気のサインとなる咳もあります。咳の仕方や咳が続いている日数など気になる点があるときは、悪化を防ぐためにも保育士から保護者に伝えてあげたいですね。今回は、咳から予想される病気や、異常を感じたときの対処法についてお伝えします。

こんな咳には要注意!
子どもは健康なときでも、1日10回程度咳をするといわれており、多くの場合は過剰に心配をする必要はありません。しかし、なかには深刻な病気の症状である咳もあります。咳の性質によっては早めの対応が必要となるので、注意すべき咳がどのようなものかを把握しておきましょう。
「コンコン」と乾いた咳は風邪の引き始めが疑われますが、ひどくならない限りは様子をみるだけでよいでしょう。注意したいのが、「ゴホンゴホン」「ゴロゴロ」という湿った咳や、「ゼーゼー」「ヒューヒュー」といったぜん息症状がみられるケースです。また、「ケンケン」といった甲高い咳は喉頭炎、仮性クループ、音のない咳は百日咳が疑われます。こうした病気のサインと感じられる咳をしている場合は、安静にするよううながし、速やかに保護者に連絡しましょう。
咳がどれくらい続いているかもチェックして
咳の種類だけでなく、咳をしている頻度やどれくらい続いているかについても観察しましょう。3週間未満でおさまる咳は急性、3~8週間続く咳は遷延性、8週間以上続く咳は慢性と判断できます。
年中昼間も咳をしていることが多く長引いている場合は、慢性の病気が疑われます。また、咳は夜間や起床時に出やすく、昼間には少なくなるものです。昼間は平気そうに見えても、咳が長引いている場合は要注意。保護者から慢性の病気に関する報告がないのに咳が長引く場合、マイコプラズマ肺炎の可能性があります。マイコプラズマ肺炎は発熱した3~5日後から乾いた咳が始まり、解熱後3〜4週間も咳が続く病気です。重症化したり、ほかの子どもに感染したりすることもあるので、気になるときは保護者に確認をとりましょう。
感染症の場合はまん延する恐れが
集団生活では、感染症の拡大を防ぐことが重要です。乾いた咳はつい風邪の引き始めととらえて油断しがちですが、RSウイルスの可能性もあります。RSウイルスは例年流行しやすいうえ、乳児が感染すると重症化する恐れもあるため、流行する時期には特に注意が必要です。また、流行した場合は、家庭でも予防してもらえるよう保護者にも注意を喚起するとよいですね。
発作のように連続で苦しそうに咳をする場合は百日咳やマイコプラズマ肺炎に感染していることがあります。疑わしい症状がある場合は、その子どものケアはもちろんのこと、保育園で流行しないように、園全体で手洗いうがい、マスク、アルコール消毒などを徹底することが大切です。
異常を感じたら速やかに対処を
咳は悪化すると呼吸困難に陥ることもあります。異常を感じたら、まずは咳に伴う症状をしっかりとチェックしましょう。
➤ 浅い呼吸を繰り返す
➤ ろっ骨が陥没する
➤ 口や肩であえぐような呼吸をしている
➤ 鼻翼が動く呼吸をしている
➤ 顔や唇の色が青ざめる
➤ 呼吸が遅くなったり、ときどき呼吸が止まったりする
➤ 失神する
これらの症状がみられる場合は速やかに保護者と医療機関へ連絡をします。また、当てはまらない場合でも、苦しそうにしているときは、安易に自己判断をしないことが大切です。
保育園は「命」を預かる場所
ふだんは平和な保育園生活でも、時に深刻な病気やけがなどが起こることもあります。保育園は子どもたちの健康と命を預かる場所であることに責任を持ち、異常を感じたら自己判断をせず、速やかに保護者や医療機関と連携をとりましょう。また、咳は感染経路でもあるため、予防策をとることも重要です。日ごろから手洗いやうがい、アルコール消毒、マスクなどの予防対策を徹底し、みんなが安全に過ごせる環境づくりを心がけたいですね。
保育の仕事の人気ランキング
おすすめ記事
人気ランキング
人気記事ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
公認ブロガー寄稿
-
保育士を辞めた人が遭遇する厳しい現実と対策
2017.01.05
特集
-
「これだけかよ…」 私が保育士辞めたい理由
2016.09.18
特集